|
アビ漁 漁師の暮らしと瀬戸内海
「聞き書き」はその人の暮らしの全体像
東京谷中の路地の中の長屋から瀬戸内海に浮かぶ小島、生口島(いくちじま)に拠点を移し、2025年4月で丁度、12年経ちました。近年、旧知の友人が発起人になって呼びかけた「聞き書き」の会『福山聞き書き人の会』(発起人
中尾圭)に加わりました。聞き書きは、自分が興味を持った方のお話しをうかがいます。ヒヤリングに似ているようですが、その人の暮らしの全体像をうかがいます。人が一人亡くなると小さな図書館が一つ無くなるようなものだと言われます。また、聞き書きは、話し手と書き手でつくる作品とも言われます。僕は、小学生時代に暮らしていた豊島(とよしま、広島県呉市豊浜町豊島)のアビ漁
漁師の西道喜代弘さん(昭和6年生まれ。当時91歳)にお話をうかがうことにしました。
鳥と人が共生する「アビ漁」
「アビ漁」という漁をご存知ですか?アビという鳥と漁業者が一体となって行う漁で、鳥と漁業者が一体となった漁は、鵜と鵜飼が思い浮かびますが、アビとアビ漁は、その様相が少し異なります。アビが自身の餌を得るためイカナゴを追ってイカナゴ漁を行い、イカナゴが渦を巻くよう集められ、そのイカナゴを食べるために、寒い時期に底にいたタイやスズキが底から上がって、アビの傍らで、それを漁師が釣り上げるのです。300年前には行われていたとされ、アビ鳥と人が共生するこの漁は「天下の奇跡です」と言われました。漁師さんは、アビは「仕事をする鳥」と言われ、冬にシベリアからやってきて最初は2週間から1ケ月ほどは同じ服を着てアビの傍に行っては戻り、鳥と仲間になるまで漁は行いません。豊島周辺にある7ヶ所の網代(アビ漁の漁場)にあるアビ神社でお祭りを行い、その年のアビ漁がはじまります。僕は、5年間、豊島に暮らしていました。アビ漁について知ってはいましたが、今回、西道さんにお話をうかがうまでは、全然知らなかったと言っていいでしょう。アビ漁は、海砂を採ったため夏眠する餌となるイカナゴがいなくなり、アビの飛来数も減り、現在、行われていません。
「アビ漁」を終えると「家船」による漁に出る
「家船」(えぶね)による漁をご存知ですか?小さな漁船で、季節による最適な漁場を求めて、「縦船」(じゅうせん)という小さな船団で仲間とともに移動します。豊島小野浦の漁師町は、家船漁師の母港として知られます(瀬戸内には、他に、忠海二窓、幸崎能地、尾道吉和、因島箱崎など、「家船」漁師の母港となる漁師町が知られています)。そして、お話された西道さんは、アビ漁が終わると、家船での漁に坂出沖瀬居島に宿をとり、二潮(ふたしお)約30日ほど出かけられるのです。その後も、屋島沖や豊後水道、米水津(よのうづ)までと、季節により広く瀬戸内海を移動して漁を行なわれたとのこと。アビ漁と家船での漁が一人の漁師の暮らしの中で連続なされていて驚きです。
西道さんを通した豊島の漁師の暮らしと生活の全体像
アビ漁はアビ漁で、家船は家船で、これまでそれぞれとても詳しく調べられ書籍もあるのですが、同じ人の暮らしの中につながっていたとは、今回、聞き書きでお話をうかがって、はじめてつながりわかりました。加えて、西道さんのお話しされる陸には立派な家があって家船の暮らしを行う「家船じゃあって家船じゃない」、と解説される豊島の漁師の家船の概念も、これまで全く聞いたことのない家船のお話で驚きの連続でした。瀬戸内の島の生活文化、一人の人の聞き書きをすることで、当時の漁師の一年間の暮らしや地域のことなど、その人を通して暮らしと生活の全体像がわかるのは、聞き書きならではないかと思います。
8編の瀬戸内コモンズ『粒粒』創刊号
等身大の地域の歴史が8編、集まる
発足した『福山聞き書き人の会』では、今回、8編の聞き書き(7編の聞き書きと1編の聞き書きを元にしたエッセイ)が集まりました。「造船」「イ草」「工業化」…。何かテーマを決めていた訳ではないのに、話の内容がつながる点があり、特に、戦後の高度経済成長期を迎えて以降の暮らしの変化が共通し、瀬戸内地域の風土や等身大の地域史が浮かび上がって面白いです。船大工の話、橋ができて渡船の仕事がなくなった話、イ草を作っていた話、環境の変化でアビ漁ができなくなった話、小さい商店が減っていった話、機関車から電車、そして新幹線開通の話など、変化が語られます。
有機的につながる共通の同時代性と同地域性
それらは、個々の変化、個々の聞き書きの中にあらわれるものだけれど、共通の同時代性かがあらわれ、8つの聞き書きが有機的につながり、実際はこのように変化して行ったのだと、これまでつながらなかったことがつながります。小さくてもその人を通した暮らしと生活の全体像がわかり、同時代の話であれば、他の聞き書きともそれらがつながりがあらわれるのは、聞き書きならではと思います。瀬戸内の暮らしが高度成長期の中でどう変化していったのか、8つの聞き書きは、それぞれに、また、相互につながり、同時代性と同地域性を表現することがわかりました。
「コモンズ」の存在
「コモンズ」という言葉があります。一般的には「共有地・物」と訳され、例えば、稲作に
欠かせない水路、茅をとるための茅場、漁場、山林など。個人に属するのではなく、それに
関わるみんなで管理したり分け合ったりする、中間領域的な存在、路地もコモンズ。「コモンズ」は、多くのスペースを空間的に必要としたり、多くの個人の時間的な制約を必要とするものではなく、だけど、人の暮らしや心に潤いや和らぎをつくる、ささやかな存在です。
空間的な「辻堂」と社会的な「青年団」
初代福山藩主水野勝成がつくることを奨励したといわれ、旧福山藩の領地と周辺に広がる”休み処”の「辻堂」はまさにコモンズの空間です。開催した勉強会「辻堂を語る会」で、なんと、現在も1,400棟を超える「辻堂」の存在が確認されているとのこと教えていただきました。驚きの数字です。中国地方や四国地方では「辻堂」の習俗が定着している地域ですが、突出した数です。「辻堂」が存在することによる、私を超えた合理性、心地よさが浸透しているのでしょう。
「辻堂」が空間的なコモンズならば、社会的なコモンズは「青年団」の活動といえそうです。福山は青年団活動の発祥の地として知られていますが、今回の聞き書きで、高度成長期以降も積極的に企業社会の人と共に青年団活動が行われていたことを知りました。暮らしの場面では、企業社会と地域社会は、青年団活動を通して共存並存していたのです。新鮮な驚きでした。
内海で空間的な一体感を持つ瀬戸内海
本州と四国との間の内海である瀬戸内海も一つの大きなコモンズとして捉えることができそうです。聞き書きの中の「アビ漁」や「渡船」の話からは、船による島同士のネットワークや瀬戸内海を広域に移動しながらの漁など、広く瀬戸内海の豊かなコモンズが暮らしの基盤となっていたことがわかります。“海を内に抱える”空間的な一体感を持つ瀬戸内海独特の営みの形といえそうです。
聞かなければ語られなかった「コモンズ」
近代化の中で、効率を重視するあまり振り落としてきたもの、「コモンズ」的なものたちに、今回の聞き書きで出会えた感覚があります。
おそらく、聞かなければ語られなかった、残されなかった話ではないでしょうか。新しい技術やそれがもたらす利便性は私たちの今の暮らしに欠かせません。一方で、「コモンズ」的なものが、私を超えた合理性、心地よさとして、私たちの暮らしを別の面で豊かにしていることも忘れてはいけないでしょう。
「聞き書き」を行うことで《つながるもの》,「聞き書き」が集まることで《つながるもの》
「聞き書き」で得られる対話(マイクロヒストリー)は、福祉や認知症の予防の役割や「人間―環境系」でいわれる「正統的周辺参加」、"生きた証"のような視点でも関心を持たれています。また、"みんなでつくった"などは「参加のデザイン」に結びつきそうです。毎回の『聞き書きの会』では、現在も学びや気づきが続いています。
「聞き書き」を行うことで《つながるもの》。そして、「聞き書き」が集まることで《つながるもの》。今回、「瀬戸内コモンズ」と呼べるような価値に僕は出会い、福山聞き書き人の会の冊子『粒粒』が2024年11月に創刊されました。
|
 |
|
1. アビの飛来数を調べた記録地図を指差しながらお話しする西道さん
|
|
|
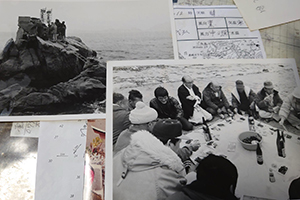 |
|
|
|
10. 置いていただける地元の本屋さん向けの宣伝用のポップ『福山聞き書き人の会』初の聞き書き集 |
|